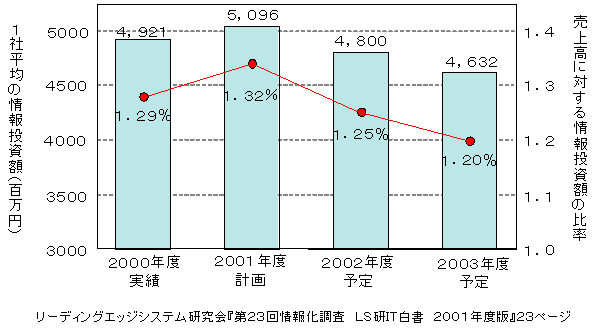情報化投資と企業収益に関する統計的分析
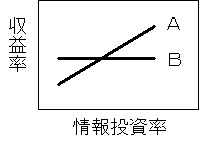
多くの企業を対象にして情報化投資と企業収益の関係を分析する研究は多く行われています。図のように,横軸に情報化投資,縦軸に企業収益をとり,多数の企業についてプロットします。情報化投資が企業収益に貢献するのであればAのように右上がりになるし,貢献しない(あるいは貢献が少ない)のであればBのように水平になります。当然,情報化投資と企業収益の2つを単純にプロットしたのではなく,企業の規模や業種などの影響を排除したり、投資と収益のタイムラグを考慮するなどの加工を行なっています。専門家の研究ですので,その点は信用してよいでしょう。
2つの分析結果
このような研究は以前から多く行われてきました。ところが1980年代までの研究では図のBのようになる結果が多かったのです。例えば,ストラスマンはゼロックスの情報担当役員や米国防総省の元国防情報部長を勤めたその道の権威ですが,『コンピュータの経営価値』という本で400ページにもわたる豊富なデータに多様な分析を試みたのですが,その結果は情報化投資と企業収益の間には明確な関係がない(すなわち図4のB)というのです。
これは経験的な感覚と一致しません。「あらゆる分野でコンピュータの時代だといわれている。ただし,生産性の統計以外では」という言葉は,ソローのパラドックスとしてよく知られています。
それが1990年代になると,情報化投資が企業収益に貢献するし,その貢献度は他の投資と比較して非常に高いという研究が続々と発表されました。たとえば,ブリンジョルフソンとヒットは,1987〜1991年のデータを用いて情報化投資の限界投資利益率(ROI)は81%にも達し,一般投資の13倍にも達するといっていますし,松平は,日本の製造業においては情報化投資によるROIは,他の投資の8.3倍にもなると算出しています。篠崎らは日本企業でも20%になるといっています。このような研究により,現在ではソローのパラドックスは解消されたというのが定説になってきました。
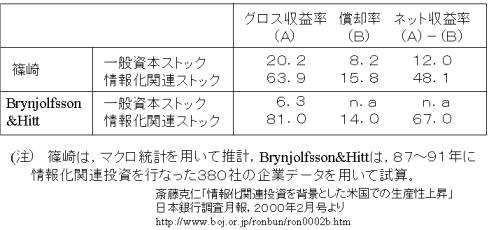
どう解釈するか
著名な研究者や実務家がデータの取り方や分析の方法に誤りがあったとは思えません。また,多数の企業を対象にしているのですから,1社の情報システムが急に改善されて収益をもたらしたとも思えません。むしろ時代的な違いにより,AからBに変化してきたと解釈するのが妥当だと思います。
- 収益に影響する分野への適用が高まった
- 肯定的な解釈では,従来とは格段に企業収益に密着する分野に情報システムが適用されるようになったからでしょう。このような動向は,インターネットの発展やBPR・SCMなどの経営技法の普及により,さらに顕著になると思われます。
- 景気の影響では?
- 否定的な解釈では,この違いは米国の景気が好転したこと自体の証明であり,情報システムの成果ではないともいえます。景気が上向くときには,積極的な投資をして少々の過剰投資をしてもすぐに吸収されます。収益向上を得た企業は積極的な投資ができる財務体質があった企業だという逆の解釈も成り立ちます。景気動向を含めた長期的な調査分析が必要なように思います。
個別企業の情報化投資と企業収益
企業を情報化投資に積極的なグループと消極的なグループに区分して,グループ間で企業収益に差異があるかどうかを分析する方法も多く行われています。
例えば,日経情報ストラテジー誌(1999年1月号)では,上場企業でインフラの整備がある程度進んでいる390社を対象に1993〜1997年度のデータを用いて,各社を情報化投資の実績から追及派・慎重派・達成派の3つに分類して,売上や収益との関係を分析しました。その結果によれば,達成派の売上高の伸び率は4%で経常利益の伸び率が8%なのに,追求派や慎重派ではともにそれぞれ1%と3%であり,社長が情報戦略に関して積極的かつ満足度の強い企業グループは,それ以外の企業グループに比べて2倍以上も業務を伸ばしています。
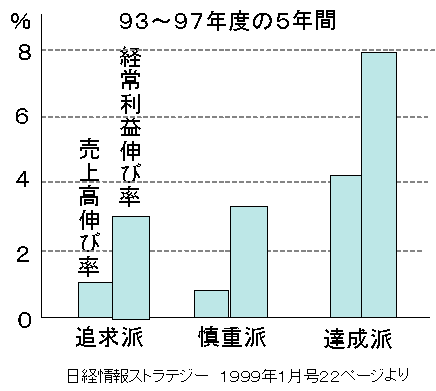
対売上比率などは意味がない
日本の経営者(情報システム部門も)は,同業他社との横並び意識が強いので,「情報化投資は売上高や経常利益の何%程度が適切だろうか?」とか「同業他社と比較して自社の情報化投資額は適切であろうか」などが気になる経営者が多いようです。そのような調査もよく行われています。しかし,このようなことはあまり意味がないのです。
その数値自体があいまい
このようなデータはアンケート調査で対象企業の情報システム部門が記入するのがほとんどです。「貴社の年間の情報化費用は?」よいう質問に,あなたは何を情報化費用だとして回答しますか? おそらく,情報システム部門の予算や実績に基づいて回答することが多いでしょう。そのとき,情報システム部門が関与しているハードウェアやソフトウェア以外の次のような費用を含むのかどうかについては,回答者により大きく異なるでしょう。
情報システム部門の人件費や事務所費用
社外向けのWebページ,技術部門のCAD・CAM,総務部門の電話など,他部門の管轄費用
利用部門の周辺機器・消耗品などの購入費
利用部門によるシステム開発やEUC指導の人件費
パソコン1台を運用する総費用をTCO(Total Cost of Ownership)といいます。ガートナーグループの調査では,TCOは購入時のハード・ソフト費用の5倍にもなるし,その総費用の約半分が利用部門の人件費だといわれています。このような見えないコストまで算出している企業もあります。
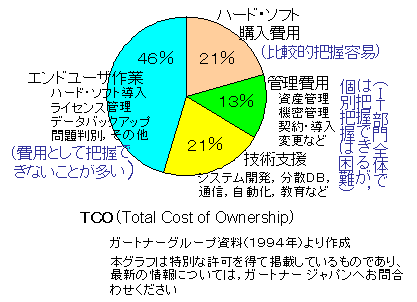
業種による違いもあります。特に情報関連企業とその他の企業では対売上比率は大きく異なるのは当然です。ところが,大企業では情報部門を子会社にしており,このようなアンケートは情報子会社が回答していることもあります。そのとき,親会社(あるいはグループ全体)として回答することもあれば,子会社だけを対象にしている場合もありますし,子会社での数値なのに親会社の業種で回答しているかもしれません。
このように,情報化費用の定義があいまいなのですから,その数値を自社の数値と比較してもあまり意味がないのです。それどころか,自社が通常よりも広い/狭い範囲で情報化費用を定義している場合には,誤った認識をしてしまう危険が生じます。
隣百姓の発想である
そもそもこのような尺度による評価は「横並び」の発想です。経営者に提案するとき「同業のA社やB社でもやっている」というのが最も説得力があります(このときC社やD社がやっていないことはいわないのですね)。同様に違う分野の情報化では,A社では「B社もC社も」となります。このようにして,同業社全体が同じような情報化をすることになります。
競争で負けることはできないので,このようなアプローチも必要なこともありますが,競争に勝つには自社のコア・コンピタンスを伸ばす分野に重点的に投資する必要があります。各社のコア・コンピタンスは異なるはずですから,情報化対象も異なるはずです。それなのに横並びで投資をしたのでは,コア・コンピタンスに投資する余裕がなくなります。
情報システム部門の費用は,ハードウェアやソフトウェアのリースや減価償却にかかる費用や既存システムの運用・小規模改訂にかかる費用のような過去からの費用と,新規システムの構築・開発や抜本的なインフラ整備に関する新規費用に区分できます。それを明確にしないで「情報システム部門予算10%削減」とすると,前者が予算の大部分を占めるのにこれは簡単にはカットできませんから,新規の案件を先送りすることになってしまいます。
そもそも関与逃避の発想である
対売上高比率などに理論的な根拠はないでしょう。それを設定するのは「自分では投資案件の評価ができないので,情報システム部門などに任せるが,野放図にすると次第に費用が大きくなってしまう。それを防ぐために,情報化投資の上限枠を設定しよう」という考えからでしょう。すなわち,情報化戦略に関するガバナンスを放棄したといえます。
これは経営者が情報化をあまり重視していないことを示したことになります。このような状況では,本当に役に立つ分野に情報化投資をすることもできませんし,情報化投資の効果を実現するための方向づけもできないでしょう。その結果,いつになっても費用対効果が改善できないのです。