現在価値法あるいはDCF法の考え方
一般的に長期間にわたる投資の費用対効果を評価するには,次のような方法を用います。
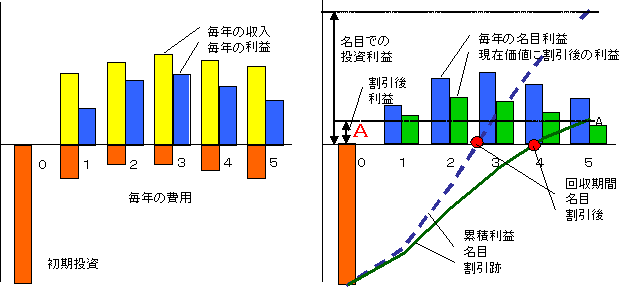
毎年の費用と収入の推定
このシステムが廃棄されるまでの期間について,それに関する初期投資と毎年の費用(赤)と収入(黄)との増加を推定します。そして毎年の利益(黄−赤→青)を算出します。
初期投資に要した費用を毎年の利益(青:これを名目利益という)で回収すると点線のようになります。この場合は3年後に回収できます。
しかし現実には現在の百万円と1年後の百万円や2年後の百万円とは価値が違いますので,毎年の利益(青)を現在価値に割り引くと緑のようになります。その結果,その累積は実線のようになります。この図では4年で回収でき,対象期間全体ではAの割引後利益が得られることがわかります。
このような計算をして,もしA≧0ならば投資案を採用し,A≦0であれば却下するというのが現在価値法です。また,ちょうどA=0になるような割引率を計算によって求めて,それが基準や他の投資よりも高ければ採用する方法をDCF法といいます。
現在価値法やDCF法などの詳細な解説は,著者のWebページ「設備投資の採算計算」(http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/dcf-intro/)を参照してください。
現実には費用も収入も将来のことですから正確な数値はわかりません。評価する人により異なることもありましょう。それに,費用にはシステムの利用方法の指導や運用での管理など把握しにくい費用もありますし,収入(コストダウン,効果)には,明確に金銭評価のできる定量的効果以外に定性的効果や戦略的効果があります。
それで,各要素について楽観的なケースや悲観的なケースなどいろいろな場合を想定して,それが発生するであろう確率も考えて計算すると,下右図のようになります。ここでは一般的には有利ですが,赤の部分のように不利になることも考えられます。
なお,このような状況のときに投資に踏み切るかどうかは,企業の置かれた環境や経営者の主観によるものですから,ここでの問題にはしません。
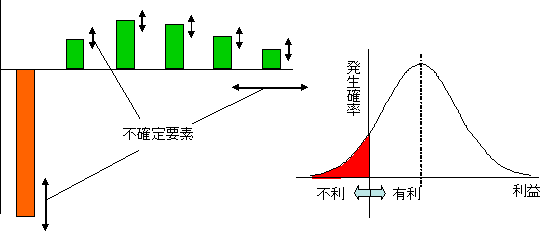
現在価値法やDCF法の限界
このような評価方法は,数学的には適切なのですが,現実の投資案を評価するには限界があります。この計算には,初期投資額,毎年の利益,毎年の損失,耐用年数,毎年の割引率が必要になりますが,その見積もりが本質的に困難な面があります。
耐用年数がわからない
DCF法の評価に大きな影響を与えるのは,対象システムの耐用年数です。常識的に毎年の収入は費用よりも大きい(利益が出る)でしょうから,たいした変更もせずに10年も利用できるのであれば,初期投資がかなりの額であっても有利になります。ところが,実施移行後1年で廃棄するような事態になれば,ほとんどの投資は不利になるでしょう。
経営環境は激変しており,情報技術は急速でしかも不連続的な発展をします。これらを予測することは経営者にも専門家にも困難です。しかも,それが発生したときにはそれに即応して大規模改訂あるいはスクラップビルドをしなければ競争に負けてしまいます。すなわち自社が予測できずコントロールできない事態が突然に発生する確率が非常に高いのです。
情報化による利益がわかりにくい
情報化投資の効果には,定量的効果,定性的効果,戦略的効果があります。
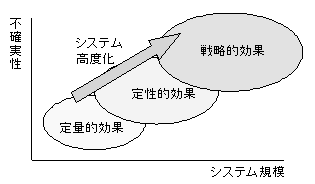
- 定量的効果
- 事務処理をシステム化して省力化が実現したことによる人件費削減のように,比較的簡単に数値的な評価ができる効果です。
- 定性的効果
- データウェアハウスにより必要な人が必要なときに必要な情報が簡単に迅速に得られるようになるとか,グループウェアにより情報伝達の迅速化や情報の共有化が得られることは,大きな効果があるのは確かですが,それを数値的に示すのは困難です。
- 戦略的効果
- カードシステムやインターネット商取引を行うことにより競争優位に立つことを目的とするシステムでは,他社に先駆けて実現すれば大きな利益が得られます。逆にもし他社が先に実現すれば大きな打撃になりますので,採算的に不利だとしても対抗上自社も開発する必要があります。
コンピュータ導入当初頃の省力化目的の情報化はいざしらず,一般の情報化投資は定量的効果だけでペイすることはむしろ稀です。定性的効果や戦略的効果を考慮しなければなりません。これらの効果を金銭的に評価するのは困難です。
見えない費用が多い
DCF法は,費用と効果がある程度の正確度で把握できることが前提になっていますが,現実にはそれが困難なのです。
費用が把握しにくい例として,クライアント・サーバーシステムの維持運営にかかる費用を考えましょう。それにかかる総費用をTCOといいますが,TCOはパソコンのハード・ソフト購入費用の5倍にもなるといわれています。その大部分は管理をしたりユーザのトラブルに対処したりする人件費です。そのうち,情報システム部門の費用は部門費用として把握できるでしょうがややあいまいになりますし,エンドユーザでの人件費などは測定すること自体が困難でしょう。
また,情報システムの構築においては,外注費用だけでなく自社の情報システム部門や利用部門の人件費がかかります。運用での人件費やライフサイクルをとおしての維持保守費用は開発時の費用よりも大きくなることもあります。これらの費用はとかく忘れがちですし,トップの承認を得たいがために,意図的に忘れることすらあります。
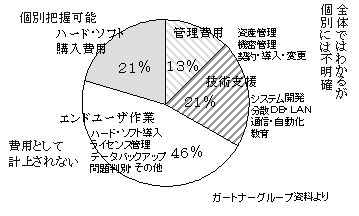
関連業務が多い
給与計算や決算処理をシステム化するのであれば,そのシステムだけの費用対効果を考えればよいのですが,それでも他のシステムとの関連を考慮する必要があります。さらにSCMやCRMなどのようなシステムでは,実際の効果をあげるには情報システム以外の多くの業務が関係します。むしろ,システム化以外の要因のほうが主であり,情報システムはそれを実現するための補助的な位置づけであるともいえます。そうなると,情報システムだけを取り上げて費用対効果を考えるのは不適切です。
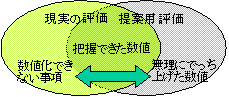
このように情報化投資では費用や効果の把握が困難な面が多いのです。当然,定量的な把握するための努力は重要です。しかし,あまりにもそれを強調するのは危険です。わからないことを強制することにより,かなり乱暴に数値がでっち上げられ,しかもその数値が作られた前提が忘れられて一人歩きをする危険があります。
しかも,関係者がこのプロジェクトの承認を得ようとして,意識的あるいは無意識的に効果面を大きく評価し費用面を小さく評価する傾向もあります。このようなバイアスのある数値化を求めること自体がナンセンスだともいえます。